ハロウィンは仮装を楽しんだり、お菓子を配ったりと、子どもたちにとってもワクワクするイベントです。
しかし、「なぜ仮装するの?」「おばけの日なの?」と聞かれたとき、幼児〜小学生にどう答えればよいのか、悩んでしまう親御さんも少なくありません。
特に年齢が小さいほど、言葉選びや説明の仕方には工夫が求められますよね。
本記事では、ハロウィンの由来を年齢別に分かりやすく伝える方法を解説します。
また、実際に役立つ絵本や遊び方、話し方の具体例も紹介するので、ぜひ親子のコミュニケーションにお役立てください。
ハロウィンの由来って何?子どもにも伝えたい基本情報

ハロウィンはもともと、古代ヨーロッパのケルト人による「サウィン祭」が由来(起源)です。
1年の終わりである10月31日に、亡くなった人の魂が現世に戻ってくると信じられており、悪霊から身を守るために仮装をしていたのが始まりとされています。
しかしながら、これを幼児にそのまま説明するのは難しいため、次のように言い換えて伝えるとよいでしょう。
このようにストーリー風に、かつ怖くなりすぎない表現にするのがポイントです。
2〜3歳向け:絵本と遊びでハロウィンの由来を楽しく伝えるコツ【絵本3選つき】
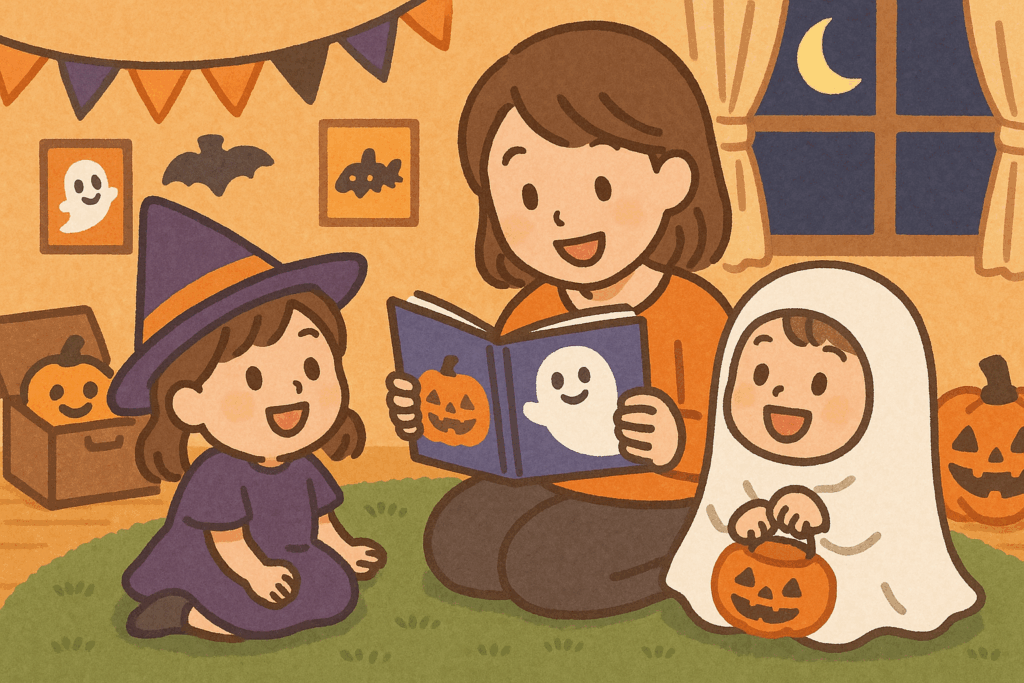
2〜3歳の子どもにとって、「由来を理解する」といっても、まだ抽象的な言葉や歴史的な背景は難しい段階です。
だからこそ、ハロウィンというイベントを“体験”として楽しむことが何よりも大切。
その中で自然と「オバケ」「仮装」「お菓子」というキーワードに親しんでいけば、それが立派な“理解”の第一歩になります。
この年齢におすすめなのは、絵本やごっこ遊びを通じて、ハロウィンの雰囲気を肌で感じてもらうことです。
絵やリズム、キャラクターの表情から「こわくない」「楽しい」という印象を持たせることで、安心感を持ってイベントに参加できるようになりますよ。
おすすめ絵本(2〜3歳向け)
- 『ハロウィン!ハロウィン!』(かしわらあきお/PHP研究所)
カラフルなイラストと「わはは!」「ふーっ!」など擬音が豊富で、リズム感のある読み聞かせが楽しめます。
読むだけで子どもが笑顔に。 - 『おばけとおともだち』(講談社)
怖くないおばけたちが優しく登場し、友達との関係性や優しさを自然に学べます。
ハロウィンに限らず日常読みとしても◎。 - 『ハロウィーンってなあに?』(主婦の友社)
「おばけってほんとうにいるの?」といった子どもの疑問に、優しく答えてくれる内容で、由来の“さわり”を紹介するのにピッタリです。
ごっこ遊びのアイデア
ごっこ遊びはこの年齢の発達にとても効果的です。
ハロウィンをテーマにした簡単なごっこ遊びは、親子のコミュニケーションにも最適ですよ。
- ぬいぐるみや人形に布をかぶせて「オバケさんごっこ」
「ばぁ!」と登場させて笑わせると、子どもも真似するように - 「トリックオアトリート!」ごっこ
お菓子を小袋に入れて、ドアの外に隠しておき「トリックオアトリート!」と声をかけたらママが渡す。「言えたね〜!」と褒めてあげると自信にも - 「かぼちゃお面」
紙皿に色紙を貼って「かぼちゃお面」を一緒に作ることで、イベントに“自分ごと”として関わらせる
このように、「絵本で知る」→「遊びで実感する」→「楽しむ」のステップを意識すれば、2〜3歳でもハロウィンの楽しさと雰囲気を十分に感じることができます。
難しい説明よりも、一緒に笑って体験することが何よりの学びですね!
4〜6歳向け:ハロウィンの由来や意味を理解する年齢にはストーリーと会話がカギ!おすすめ教材つき

4〜6歳は、物語を理解したり「なぜ?どうして?」と理由を知りたがる時期。
この年齢の子どもには、ハロウィンの由来や背景を、シンプルなストーリーとして語ることで、興味を持ってもらいやすくなります。
単なる「おばけごっこ」のイベントではなく、「昔の人がどうして仮装したのか」まで、少しだけ掘り下げて伝えてみましょう。
たとえば、以下のような話し方が効果的です。
このようにストーリー仕立てで話すと、子どもは「なるほど、だから仮装するんだ」と納得しやすくなります。
そこに「お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ!」という遊び要素を加えると、興味をより引き出せますよ。
会話のキャッチボールで理解を深めよう
また、親子の対話を大切にすることもポイントです。
たとえば以下のような質問と答えを通じて、自然と由来を学べます。
子:「なんで仮装するの?」
親:「オバケに見つからないようにするためだったんだって!」
子:「どうしてお菓子もらえるの?」
親:「“いたずらしないでね”ってお願いする気持ちであげたんだよ」
子どもが納得したように「ふーん、じゃあわたしも仮装したらいいね!」と返してきたら、それは“理解したサイン”です。
4〜6歳におすすめの動画・教材
- 【YouTube】しまじろうチャンネル「ハロウィンってなあに?」
ストーリー仕立てで紹介しており、仮装の意味や文化の違いにも触れられる - 【NHK for School】キッズ特集ページのハロウィン回
「おばけがきたらどうする?」など、考える力を育む構成 - 【英語絵本】『Clifford’s Halloween』
わかりやすい英語で、赤い犬のクリフォードが仮装で大活躍
この時期の子どもは“知ることが楽しい”と感じ始める年齢です。
だからこそ、「なぜ?」に答えるストーリーと、親子で対話する時間が、ハロウィンの理解をぐっと深めてくれます
大人にとっても、文化や歴史を振り返る良い機会になるでしょう。
小学生向け:文化や歴史の視点でハロウィンの由来を深く知ろう
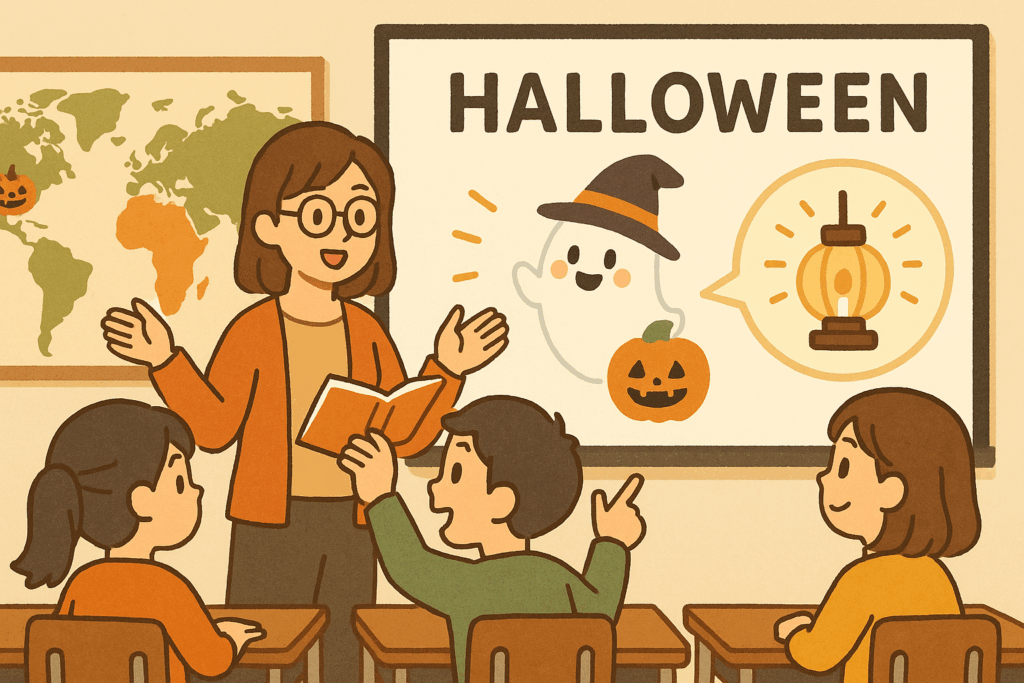
小学生になると、「なんで?」「どうして?」という疑問がより具体的になってきます。
ハロウィンについても、ただ楽しむだけでなく、その起源や世界との違い、さらには意味の深さまで学びたがる時期。
そのため、この年代には“文化としてのハロウィン”を少し踏み込んで伝えるのが効果的です。
たとえば、ハロウィンはもともと古代ケルト人が行っていた「サウィン祭」に由来し、「死者の魂がこの世に戻ってくる日」として信じられていたことを紹介しましょう。
そして、悪い霊から身を守るために仮装をしたことが、今のハロウィンに繋がっているという歴史的背景を伝えます。
さらに、
といった対比を示すと、子どもたちも理解が深まります。
英語学習ともつながるハロウィン
小学校では英語の授業も始まり、「Trick or Treat!(お菓子をくれなきゃいたずらするぞ)」のフレーズを覚える機会もあります。
こうした言葉の背景や、海外でのハロウィンの様子(たとえば玄関を飾ったり、家ごとにテーマを決めて仮装したりする文化)を紹介すると、言語と文化が自然につながる体験になります。
おすすめの調べ学習・自由研究テーマ
- ハロウィンの起源を調べて年表にしてみる
- 日本と海外の「死者を想う行事」を比較してまとめる
- 自分だけの仮装デザインを考えてポスターにする
このように、小学生には“楽しい”に“学び”を加えて、ハロウィンを自分なりに深く理解できるよう導いてあげましょう。
文化や歴史に触れることで、ハロウィンがただの仮装イベントではないことに気づくきっかけになります。
まとめ
ハロウィンは、子どもにとっては「仮装してお菓子をもらう楽しい日」ですが、その背景には文化的・歴史的な意味が込められています。
2〜3歳の子どもには、絵本やごっこ遊びを通じて“楽しい”気持ちを育てることが第一歩。
4〜6歳には、ストーリー仕立てで「なぜ仮装するのか?」を優しく伝えると、理解が深まります。
小学生には、海外の文化としてのハロウィンや、日本のお盆との違いを比較しながら、調べ学習や英語表現にもつなげていくことで、イベントとしての楽しさと学びが両立できます。
単に行事を“こなす”のではなく、親子で会話し、共に理解を深める機会にすることで、ハロウィンはもっと豊かな体験になります。
2025年のハロウィンは、ぜひ年齢に応じた伝え方で、子どもたちと一緒に「知って・楽しんで・深める」1日にしてみてくださいね。


